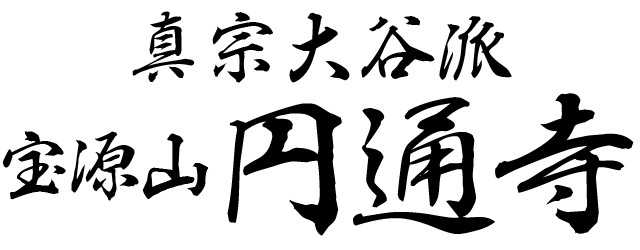行事について
円通寺や河合谷地区でつとめられている行事についてご説明いたします。
蓮如上人御崇敬(れんにょしょうにん ごそうきょう)
蓮如上人御崇敬は、鹿島・羽咋郡市全域で行われている歓喜光院殿御崇教(※)が盛んなことを知り、地域での信仰をさらに深めるべく本願寺中興の祖とされる本願寺八世蓮如(れんにょ)上人を偲ぶ法要として明治30年頃に始まりました。
現在は宝達志水町とかほく市(旧南大海村)及び津幡町(旧河合谷村)の一部を5つの地区に分け、寺院と門徒が協力して持ち回りで運営を行っており、毎年3月1日に勤められています。
(※)歓喜光院殿御崇教・・・死者2600人と言われる天明8(1788)年の京都大火で焼失した京都市内や本願寺の本堂など寺院の再建・復興のために大勢の能登地方の門徒が工事を手伝いやお金を納めたお礼として、東本願寺の第19代法主乗如(じょうにょ)上人(歓喜光院殿)の御影(掛け軸になった肖像画)を授与されたことから、享和2(1802)年に羽咋市の本念寺で第1回の歓喜光院殿御崇教が営まれ、以後幕府が集会を禁じた2年を除いた210余年にわたり毎年営まれています。
祠堂経(しどうきょう)・永代経(えいたいきょう)
「祠堂経」(または「永代経」)とは、お寺が存続し教えがますます盛んになるようにとの思いから勤められる法要です。
故人を縁としてお寺に参詣することによって、ご先祖への追慕とともに、日頃、煩悩にまみれた生活を送っている自分自身が聞法と感謝と喜びをいただく行事です。
懇志をあげられた場合に、その都度お勤めすることもありますが、お寺では年に1回、一括して勤められるのが通例です。
祠堂とはお堂を祠るということで、門徒の方々のお寺をまもる志「布施」に対し、末代までもおつとめさせていただこうという「法施」が永代会です。この二つが一つになって永代祠堂会とか永代祠堂経会と呼ばれます。
「永代」という言葉がつくと、他宗で用いられる「永代の供養のためにまとまったお金を納めお寺にお願いする」と勘違いされることがありますが、浄土真宗では趣が異なり、故人を縁として永代に仏の教えが伝えられることを願って勤められる仏事です。
護法会(ごほうかい)
護法会とは、津幡町の河合谷地区の真宗寺院8ケ寺(大谷派6ケ寺・本願寺派2ケ寺)が毎年持ち回りで行い、地区で亡くなった友人や知人を追悼する会です。
明治22(1889)年の旧憲法(大日本帝国憲法)発布に伴い、仏法も盛んにとの願いが込められて発足したのが「発憲護法会(仏法を守護する)」です。その後、太平洋戦争の敗戦に伴い、新憲法(日本国憲法)が公布されたことにより「発憲」の字句が外れ、「護法会」と呼ばれています。
毎年7月1日に勤められ、過去には年2回勤められたこともありました。
地区内住民の減少や高齢化で運営が難しくなったため、令和元年(2019年)に勤められた第147回目をもって終了となりました。今後は各寺院で勤められる、「祠堂経」及び「永代経」がその役割を担っていくことになります。
報恩講(ほうおんこう)
報恩講の起源は、本願寺三世の覚如(かくにょ)上人が親鸞聖人の三十三回忌に『報恩講式』をまとめたことといわれており、浄土真宗の僧侶や門徒にとっては、私たちに救いの手を差し伸べてくださる阿弥陀様の教えを脈々と伝え、一人ひとりに生きるよりどころ(道)を示し阿弥陀仏の念仏をすすめられた親鸞聖人の恩に報いる集まり(講)は、一年の中で最も重要な仏事です。
日頃、人だけでないあらゆるものから受けた恩に気づく(知る)ことによって自然と報いる(お返しをする)機会で、自分たちが報恩と感謝の心によって生かされていることに改めて気づかされる場です。円通寺では、毎年11月4日・5日にお勤めしています。
真宗大谷派の本山・東本願寺では、毎年11月21日から28日までの8日間勤められ、親鸞聖人の御命日である28日には、「坂東曲(ばんどうぶし)」が勤められます。
坂東曲とは、東本願寺でのみ勤められる独特の声明(しょうみょう)で、親鸞聖人が越後へ流罪になる際、荒波に揺れる船の中で一心に念仏を唱えたお姿を再現したとも言われています。出仕した僧侶が正座をしたまま上体を力強く前後左右に動かしながら独特の節回しで念仏・和讃を唱和します。